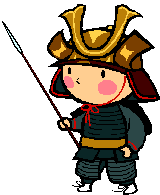トップページ » コラム » ちょっと一息メンタルケア » 「思いやり」が「重い槍」にならないように
![]()
May 30th 11
「「思いやり」が「重い槍」にならないように」
今回の大震災で、東北の人の我慢強さや奥ゆかしさ、ひいては日本人の「他人を思う」国民性が海外では大きく評価され、少し誇らしい気持ちにもなりました。
思いやりのスタートは、相手の事(状態や気持ち)をこちらが想像することから始まります。想像するためには、「あの人はいつもこうだから」と自分が知っているその人の情報を元にしたり、「自分ならこうする」と、自分の方法を元にするなど様々だと思います。
「思いやる」という行為には、相手のことを勝手に思い込んだり、自分を我慢させてしまうという側面もあります。「他人を思いやる」ために自己を過度に抑えてしまうこと、ありませんか? 溜めこむと、怒りとして爆発したり、大きなストレスになり自分の健康を損ねかねません。
ここで大事なのは、「思いやる相手」というのは、あくまで「自分が想像している相手」だということです。せっかくの思いやりが、うまく伝わっていない時は、こちら側の「勝手な思い込み」が先行して、相手のニーズに合っていない、ということが多いようです。
やがて、自分の思いやりという善意に対して反応がこないことに苛立ちが出始めて、「やってあげているのに」と怒りの感情にも結びつきかねません。
実際に被災地ではこんなことが起こっていると聞きました。
被災されている方に「何が必要か」を確認し、相手も「不要なものは断る」という協議が出来た被災地では、具体的な支援が多く受けられようですが、
あるエリアでは、寄せられた善意に対して「せっかくの思いにリクエストを入れるのは忍びない」と物資をそのまま受け入れて、かえって不要なものが出てしまい、対応に苦慮されていると。
受けた方も的外れな善意だと、その思いはありがたいが、かえって迷惑。それが継続してしまうと相手に対してネガティブな感情の湧きかねません。
そもそもは、善意からのスタートなのに、残念な結果になるのはもったいないですね。
大事なことは、自分の想像が的外れでないかどうかの確認をすること。
よりよい関係を保つためには、自分の気持ちや考えを伝え、相手の気持ちや考えを確認して、協議すること。簡単にいえば「私はこう思うけど、あなたはどう?」というキャッチボールをすることが大事だと思うのですが、いかがでしょうか。
「ちょっと一息メンタルケア」一覧へ
![CI・ブランド戦略 [ コアコード株式会社 : コラム ]](../../img/whiteboard.jpg)